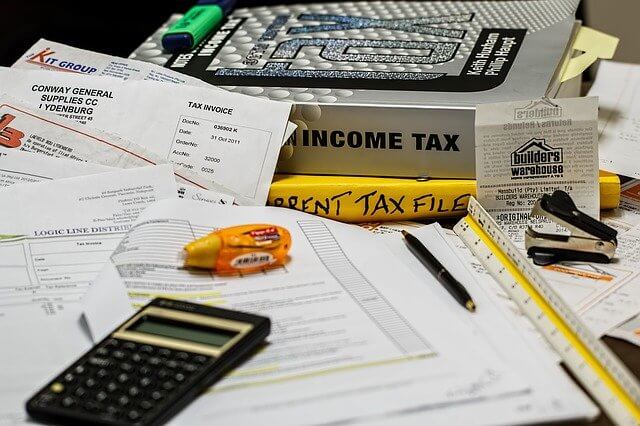面倒だけどちゃんと終わらせなきゃいけない確定申告、みなさん準備は進んでいますか?
確定申告は特定の期間内に、申告から納税までを済ませなければいけません。
確定申告めんどくさいよ〜
いつも準備してないのが悪いんだけど…— Anne (@Ann_e7s) February 23, 2021
確定申告時期に入ってたのすっかり忘れてて今せっせと準備中だけど、ほんとめんどくさいわねこの手続き( ´•ω•` )
でもちゃんと申告終わらすぞー(´°ω°`)— mori- (@ff14_moriiiii) February 22, 2021
万が一、納税が遅れたり無申告のまま放置したりすると、ペナルティとして延滞税や無申告加算税などが発生します。
時間やお金が無駄にかかってしまうので、確定申告は必ず済ませておきましょう。
本記事では、確定申告の準備をする際に用意しておく書類やものについて解説します。
個人事業主・サラリーマン・年金受給者とケース別に解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
確定申告の準備は余裕も持って!申告期間は?

確定申告の準備を進める前に、申告期間について確認しておきましょう。
原則、確定申告の期間は翌年の2月16日~3月15日です。
3月15日までに、税務署に所得税の納税額を申告して納税を済ませましょう。
2021年の確定申告の期間は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が申告期間と重なるため、令和3年4月15日の木曜日までに延長されています。
確定申告会場の混雑を回避するためですね。
申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消 費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月 15 日(木)まで 延長することといたしました。
(引用:国税庁 報道発表資料)
2021年の確定申告は、4月15日までに所得税の納税までを済ませましょう。
確定申告は面倒ですが、無申告のまま放置するとペナルティが発生します。あとから追加で税金が発生するうえに、手続きで時間もかかってしまいます。
ですので、確定申告を行う必要がある方は、必ず申告しましょう。確定申告の無申告がバレるとどうなるのかについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
確定申告前に準備する必要書類・必要なもの
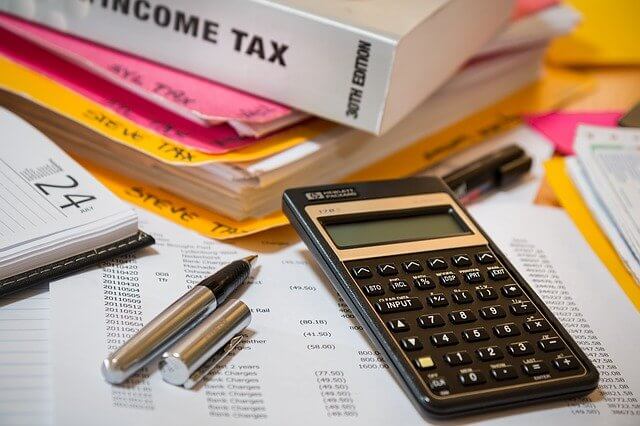
それでは、確定申告の準備を進めていきましょう。
本項目では、個人事業主・サラリーマン・年金受給者が、共通で準備すべき書類やものについて解説します。
確定申告書
確定申告では、確定申告書を税務署に提出して納めるべき所得税を申告します。
確定申告書には、以下の4種類があります。
・確定申告書B
・分離課税用(Bと併用)
・損失申告用(Bと併用)
そして、各種申告書の特徴は以下のとおりです。
| 書類 | 特徴 |
| 確定申告書A | 主に給与所得者・年金所得者が使用 |
| 確定申告書B | 主に個人事業主・フリーランスが使用 |
| 分離課税用 | 土地や建物、株式などを譲渡した際に得た所得、退職所得など分離課税対象の所得を申告する場合に使用 |
| 損失申告用 | マイナスの所得を申告する際に使用 |
確定申告書は、国税庁のホームページや税務署で入手できます。
以下の国税庁のリンクからもダウンロードできるので、印刷しておきましょう。
・確定申告書Aのダウンロードはこちら
・確定申告書Bのダウンロードはこちら
本人確認書類
確定申告を行う際、申告者が本人であると証明するために、本人確認書類が必要です。
以下の書類を用意して、確定申告に備えましょう。
| 身元確認書類 | 運転免許証・パスポート・在留カード・公的医療保険の被保険証など |
| 番号確認書類 | マイナンバーの記載がある通知書 または 住民票 |
金融機関の通帳もしくは口座番号
税務署に申告した所得税を口座振替で納付する場合、ご自身名義の銀行口座の番号が必要です。
還付申告をする際も同様です。
所得証明書類
確定申告書に収入と所得を記載する際、関連の書類が必要です。
申告する所得の区分によって、準備する書類が異なります。
以下の表をご覧ください。
| 申告する所得の区分 | 用意する所得証明書類 |
| 給与・年金・報酬・賃金など | 源泉徴収票の原本・支払調書の原本 |
| 雑所得・配当・一時所得 | 所得の内容を証明する書類 |
| 事業所得・不動産所得 | 青色申告決算書 または 収支内訳書(白色申告の場合) |
| 株式取引の所得 | 年間取引計算書 |
| 土地や建物を譲渡して得た所得 | 譲渡時の売買契約書・購入時点の契約書・仲介手数料や印紙代の領収書など |
2019年4月1日以降、確定申告書に源泉徴収票の原本を添付する必要はなくなりました。
ただし、税務署の相談会場にてご自身で確定申告を行う際は、持参が必要です。
詳細は国税庁のホームページ「国税関係手続が簡素化されました」を確認してください。
控除書類
還付申告を行う際、以下の書類を確定申告書に添付します。
受ける控除によって準備する書類が異なるので、確認しておきましょう。
| 内容 | 準備する書類 |
| 医療費控除 | 医療費の領収書・明細書 |
| 社会保険料控除 | 社会保険料、国民年金保険料控除証明書 |
| 生命保険料控除 | 支払額がわかる証明書 |
| 地震保険料控除 | 支払額がわかる証明書 |
| 寄附金控除 | 寄附した団体・法人から交付された受領書 |
| 配当所得 | 配当の種類に応じた支払通知書 特定口座年間取引報告書 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 掛金額の証明書 |
| 勤労学生控除 | 学校や法人から交付を受けた証明書 |
| 住宅ローン控除 | 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 住宅借入金残高証明書 住民票の写し など |
| 政党等寄附金特別控除 | 政党等寄附金特別控除額の計算明細書 寄附金(税額)控除のための書類 |
還付申告で納めすぎた税金を取り戻したい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
印鑑
確定申告書類には、朱肉を使った印鑑で押印します。シャチハタは使用できないので注意しましょう。
口座振替を申請する際は、銀行の届出印も準備してください。
確定申告前に準備する書類|個人事業主
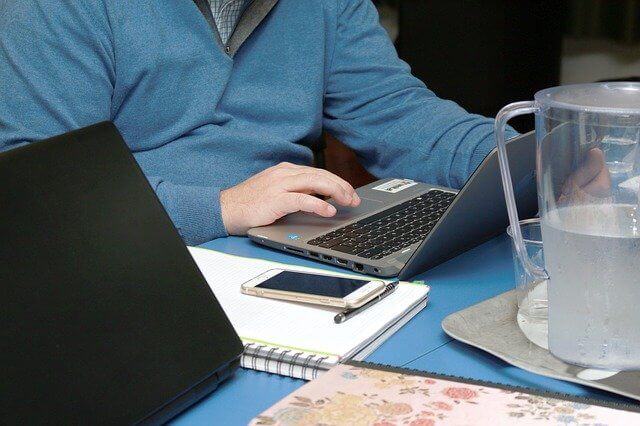
個人事業主の方の確定申告は、青色申告か白色申告で行います。
青色申告と白色申告の特徴は、以下のとおりです。
| 種類 | 特徴 |
| 青色申告 (55万円控除) |
複式簿記で記帳を行う 帳簿の保存義務あり 3年間の赤字の繰越あり 事前の届け出が必要 |
| 青色申告 (10万円控除) |
簡易簿記で記帳を行う 帳簿の保存義務あり 3年間の赤字の繰越あり 事前の届け出が必要 |
| 白色申告 (控除なし) |
簡易簿記で記帳を行う 帳簿の保存義務あり |
確定申告は申告方法によって、節税効果の大きさが異なります。
節税効果は、申告方法が複雑で難しいほど大きいです。
青色申告を行う場合は、納税地の所轄税務署に青色申告承認申請書を提出しましょう。
白色申告は2014年1月から、帳簿への記帳・保管が義務付けられています。簡単に収支を記帳すればいいので、税の知識がない方でも簡単に書類を作成できます。
それでは、各種申告の必要書類について見ていきましょう。
白色申告の必要書類
白色申告を行う際の必要書類は、以下のとおりです。
| 申告の種類 | 必要書類 |
| 白色申告 (控除なし) |
確定申告書B 収支内訳書 |
青色申告の必要書類
青色申告を行う際の必要書類は、以下のとおりです。
| 申告の種類 | 必要書類 |
| 青色申告 (55万円控除) |
確定申告書B 青色申告決算書 (貸借対照表・損益計算書) |
| 青色申告 (10万円控除) |
確定申告書B 青色申告決算書 (損益計算書) |
確定申告前に準備する書類|サラリーマン

続いては、サラリーマンが確定申告時に準備する書類を、受ける控除別に紹介します。
サラリーマンの方は、基本的に確定申告を行う必要がありません。会社が源泉徴収で給与から税金を差し引いて、年末調整で納税額の計算・調整を行なっているからです。
代わりに確定申告を行なってくれているようなものですね。
ただし、年末調整時に処理できなかった控除申請がある場合、控除を受けるには確定申告を行う必要があります。
詳しく見ていきましょう。
ふるさと納税をしている
ふるさと納税を行なった方は、納税額に応じて寄附金控除を受けられます。控除を受ける条件は、以下のとおりです。
・納税先に寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出している
そして、確定申告を行う際に準備する書類は、以下のとおりです。
・源泉徴収票
・寄附金受領証明書(領収書)
・特定公益増進法人である旨の証明書(写し)
・特定公益信託である旨の認定書(写し)
寄附金受領証明書には、寄附先の所在地や寄附額などが記載されています。
確定申告書を作成する際に必要な内容が記載されているので、準備しておきましょう。
住宅ローン控除を受ける
ローンを組んで住宅を購入したりリフォームした方は、住宅ローン控除を受けられます。
住宅ローン控除を受けるには、初年度のみ確定申告を行う必要があります。2年目以降は年末調整で処理されるため、確定申告は不要です。
確定申告時に必要な書類は、以下のとおりです。
・源泉徴収票
・住民票(写し)
・登記事項証明書(原本)
・借入金残高証明書
・不動産売買契約書(写し)
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
借入金残高証明書は、金融機関から翌年の1月下旬ごろに送付されます。
確定申告時に必要なので、準備しておきましょう。
医療費控除を受ける
年間の医療費が一定額以上かかっている方は、医療費控除を受けられます。控除額の計算式は以下のとおりです。
医療費控除を受ける方は、以下の書類を準備してください。
・源泉徴収票
・医療費控除の明細書
医療控除の明細書は、税務署か国税庁のホームページでダウンロードできます。医療費を計算して、書類に記載しましょう。
・医療控除の明細書のダウンロードはこちら
健康保険組合などから医療費通知が交付されている場合は、確定申告時に添付してください。医療控除の明細書の記載を簡略化できます。
そして、医療費の領収書の保管は不要です。
ただし、確定申告時に添付できる医療費通知には、以下の条件があります。
・被保険者等の氏名
・療養を受けた年月
・療養を受けた者
・療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
・被保険者等が支払った医療費の額
・保険者等の名称
(引用:国税庁 医療費通知の利用について)
雑損控除を受ける・災害減免法を利用する
盗難や自然による経済的な被害にあった方は、雑損控除を受けられます。確定申告時に、災害による支出領収書を添付しましょう。
また、年間所得が1,000万円以下の方であれば、災害減免法の適用を受けられます。損害金額明細を準備して、確定申告時に添付してください。
控除額が多い方を選択して、必要書類を準備しましょう。確定申告時に準備する書類は、以下のとおりです。
・源泉徴収票
・災害による支出領収書(雑損控除)
・損害金額明細(災害減免法)
特定支出控除を受ける
テレワークや出張などで仕事による支出が増えた方は、特定支出控除を受けられる可能性があります。
控除対象は、仕事の経費の合計金額が、給与所得控除額の半分以上となる方です。
給与所得控除額を、以下の表で確認してみましょう。
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)給与所得控除額 1,625,000円まで 550,000円 1,625,001円から1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円 1,800,001円から3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円 3,600,001円から6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円 6,600,001円から8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円 8,500,001円以上 1,950,000円(上限) (引用:No.1410 給与所得控除 国税庁)
(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。
特定支出控除を受けられる方は、以下の書類を準備してください。
・源泉徴収票
・会社が発行した証明書
・経費が発生したと証明できる書類
特定支出控除について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
2か所以上から給与を得ている
副業で2か所以上の会社から給与などの収入を得ている方は、確定申告を行いましょう。
副業の収入は、年末調整で処理できないからです。ですので、以下の書類を準備して確定申告を行いましょう。
・本業の源泉徴収票
・副業の源泉徴収票または副業の支払調書
年末調整で控除の申告漏れがある
年末調整で処理できなかった所得控除は、翌年に確定申告を行えば受けられます。
以下の書類を準備して、確定申告時に添付してください。
・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
・地震保険料控除証明書
・国民健康保険控除証明書
・国民年金保険料控除証明書
など
他にも受けられなかった控除がある場合は、証明書を用意して添付しましょう。
会社を途中退職して年末調整を受けていない
会社を途中退職した場合、翌年に確定申告が必要です。退職から1ヶ月以内に、会社から源泉徴収票が送られてきます。
確定申告の際に持参して、確定申告書に添付しましょう。
確定申告前に準備する書類|年金受給者

年金受給者の方でも、一定の条件を満たすと確定申告が必要です。
確定申告が必要な条件は、以下のとおりです。
②雑所得以外の所得(公的年金含む)が20万円を超える
③各種所得控除を受ける
所得控除を受ける場合は還付申告なので、必ず確定申告が必要なわけではありません。しかし、①と②に該当する方は確定申告が必要です。
以下の書類を準備して、確定申告を行いましょう。
・公的年金等の源泉徴収票
・各種控除を受けるために必要な証明書
年金以外の所得に注意して、確定申告が必要かどうかを判断しましょう。
確定申告の準備でやっておきたいこと

確定申告の準備で揃える書類について解説しました。
必要書類をきっちり揃えて、確定申告時に確定申告書に添付しましょう。
最後は、確定申告の準備のために、普段からやっておきたいことについて解説します。すでに申告期間中の方は、今年から来年の確定申告に向けて準備してみてください。
それでは見ていきましょう。
控除証明書や領収書は必ず保管しておく
控除証明書や領収書は、必ず整理・保管しておきましょう。確定申告書を作成したり所得控除を受けたりする際に必要だからです。
そして、確定申告後に税務署から確定申告について問い合わせがある場合にも、提示する必要があります。
さらに、書類には保存期間が定められているので、確認しておきましょう。
保存する書類 保存期間 収入金額や必要経費を記載した帳簿
(法定帳簿)7年 業務に関して作成した上記以外の帳簿
(任意帳簿)5年 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年 (引用:国税庁 帳簿書類の保存期間)
確定申告後に安心して、書類を捨てないようにしてください。
帳簿の記帳をサボらない
普段からこまめに帳簿をつける癖があると、確定申告の準備が楽になります。週・月単位でまとめて帳簿をつけるのは大変ですよね。
どうしても記帳の間隔を空ける方は、領収書やレシートを月単位で分けておきましょう。次回まとめて帳簿をつける際、スムーズに作業を行えます。
取引先や科目で分けたり、ご自身にとってわかりやすいように整理してみてください。
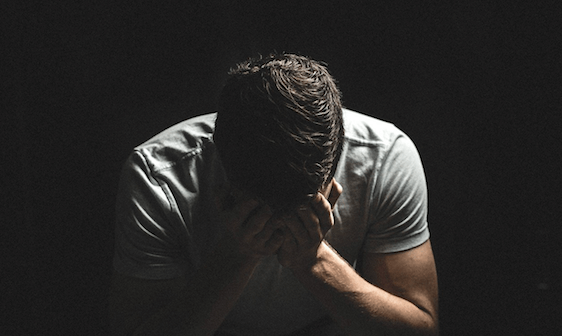


そんな方は、以下の問い合わせフォームからご相談ください。
弊所では、確定申告の代行を承っております。確定申告で悩みを抱えている方は、まずはお気軽にご連絡ください!